受付時間 | 午前10:00から午後18:00 |
|---|
休業日 | 土日祝日 |
|---|
※事前に予約していただければ時間外・休日
も対応いたします
相続登記の義務化について

相続登記のルールが変わります
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
この点について
①どんな人があてはまるのか
②あてはまったら何をすべきか
③しなかったらどうなるのか
④令和6年4月1日より前の相続登記はどうなるのか
⑤相続登記をすることが難しいときはどうしたらいいのか
を解説していきます。
どんな人があてはまるのか

不動産がある場合だけです
この制度の対象になる人は
相続(遺言もふくみます)によって不動産を取得した相続人です。
亡くなった方が株式や銀行口座しかもっていなかった場合には関係ありません。
あてはまったら何をすべきか

3年の期限があります
そして不動産を取得した相続人は、それを知った日から3年以内に相続登記を法務局に対してしなければなりません。
一般的な例でご説明します。
・亡くなった方の相続人が奥様と子供
・亡くなった方名義の不動産(通常は住んでいた建物とその底地)がある
この場合、相続する不動産があることと自分が相続人であることは、お亡くなりになられた時点でわかると思います。
つまりこの場合には、亡くなった時から3年以内に不動産の名義を相続人にかえる手続きをする必要があります。
ここでご注意いただきたい点があります。
注意点
相続人全員の相続登記をした後に遺産分割をした場合
相続時の不動産の名義は、上記の例でいえば奥様の名義になることが多いと思います。
その場合は、最初から遺産分割協議をして奥様の名義にする登記手続きをします。
ただ誰の名義にするか決まっておらず、とりあえず相続人全員の名義を入れた後に協議で決まった人の名義にする、ということが今回の相続登記義務化の影響で考えられます(3年以内の登記という制約があるので)。
そうすると相続人全員名義の登記をした後に、協議で決まった人に名義をかえていくという登記手続きをすることになります。
このときの遺産分割協議にもとづく登記手続きについても協議の成立した日から3年以内という制約があります。
つまり相続登記自体は3年以内にしたのだけれど、遺産分割協議をした後の登記は3年を経過してしまった場合、やはり相続登記の義務違反ということになっていまいます。
しなかったらどうなるのか
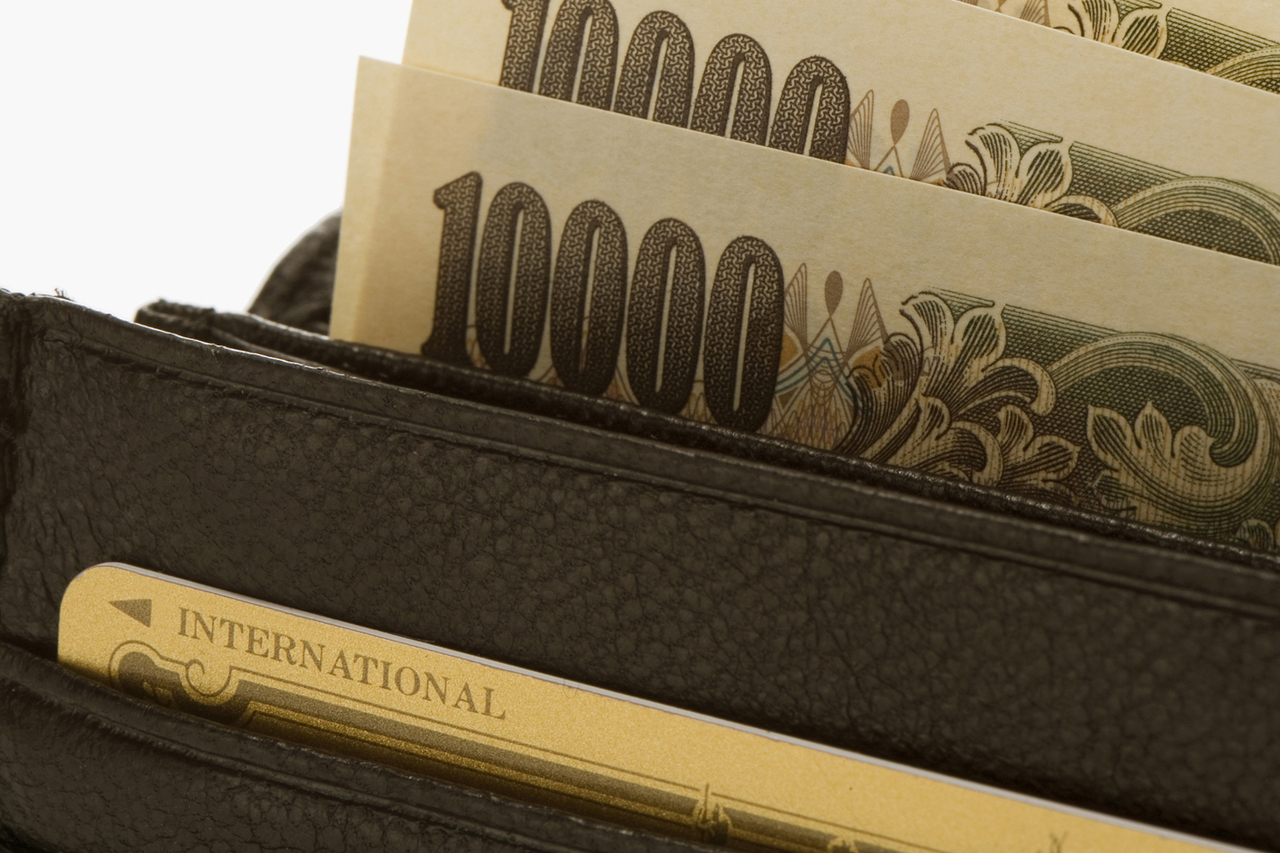
無視できない金額です
正当な理由もないのに相続登記の義務に違反した場合
10万円以下の過料(行政上のペナルティー)を課せられます。
令和6年4月1日より前の相続登記はどうなるのか

前の相続も対象になる場合があります
令和6年4月1日より前に始まった相続でまだ登記していない不動産についても義務化の対象とされています。
この場合、3年の猶予期間があります。
これは相続等により所有権を取得したことを知った日、または令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする必要があるという意味です。
相続登記をすることが難しいときはどうしたらいいのか

新しい登記手続きです
たとえば、相続人の数が多くて協力をあおぐことが難しい、または遺産分割協議がまとまらず登記までいたらないなどの事情がある場合。
このようにすぐに相続登記をすることが困難な事情がある場合、相続人申告登記という手続きがあります。この手続きは通常の相続登記よりも簡易な手続きであり、それを3年以内にすることで申告した人は10万円以下の過料をうけることはなくなります。
ただこの場合にも、遺産分割協議が成立した場合には速やかに相続登記を行う必要があります。
相続登記のご用命ございましたら

相続登記をするには、戸籍を集めて、登記にかかる税金を計算して、申請書を書いて法務局に提出するといった手続きが必要になります。
当センター(司法書士事務所黒船)では、そんな煩わしい手続きを相続人の皆様に代わって行うお手伝いをさせていただいております。
戸籍集め、登記申請、どちらも全国対応で対応させていただきます。
今回の相続登記義務化によりその必要性を感じられたなら、ぜひ当センターのサービスをご検討ください。
アクセス・営業時間
住所
〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1152番地15
オークタス蕪木101
受付時間
10:00~18:00
(事前予約があれば時間外も対応可)
休業日
土・日・祝日
(事前予約あれば休日も対応可)
